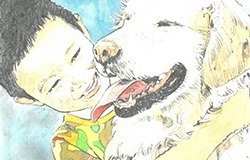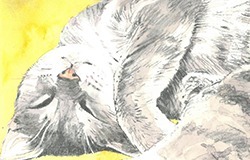ブログ
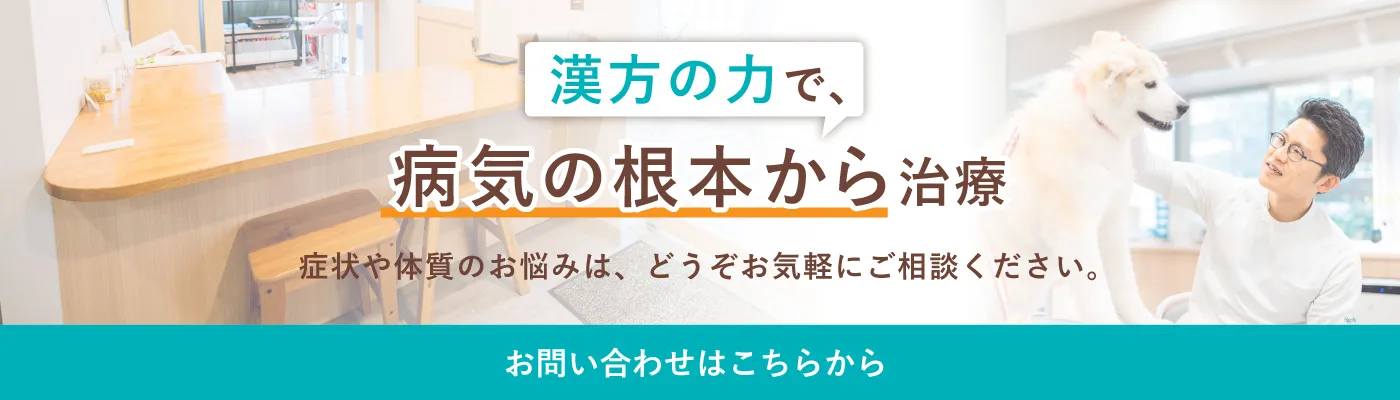
- 【ペットの病気予防】体を根本から整える東洋医学的な寒さ対策とは
-
- 2025/11/15
- 治療方針、その他
-
夏の冷房や秋冬の冷える季節は、ペットの体が冷えて不調や病気を引き起こす可能性があります。そのようなペットの不調や病気を防ぐには、日頃の様子を観察して、冷えのサインを見逃さいようにすることが大切です。
冷えによる症状が起こった場合は、症状を抑えるだけの治療ではなく、冷えを改善する根本的な治療が欠かせません。「具体的にどのような対策が必要なの?」という疑問を解消するために、今回は、ペットの体を根本から整える東洋医学的な寒さ対策について解説します。
また、すぐにできる室内・散歩・外出時の寒さ対策も紹介しますので、その子に合った方法を見つけて取り入れてみましょう。
ペットの寒さ対策は必要?冷えが引き起こす不調や病気

「ペットは寒さに強い」と考えている方がいるかもしれませんが、冷えの症状を見逃すと不調や病気を引き起こす可能性があるため、適切な対策が必要です。まずは、冷えが引き起こす病気や不調、ペットの冷えのサインを解説します。
あまり外出していないけど冷え対策は必要?
「室温を夏と同じに設定している」
「外もあまり出てない」
だから「冷えは大丈夫」と思っている人が多いのですが、それでも秋冬は冷えている子が多いです。同じ室温でも夏と冬では体のバランスが違ったり、窓から入ってくる日の強さも違うので、冬は冷えてしまいます。
また、エアコンだけでなく、暖房の暖かい空気は上にいくので、ペットがいる床付近は設定温度よりも低くなりがちです。人でも、同じ22~23度の部屋では、夏だと半袖でも平気ですが、冬の室温22~23度で半袖は寒く感じるのと同じです。
ペットの冷えのサイン
ペットが寒いと感じているときは行動や見た目、体などに変化が現れます。以下のようなサインが見られたら、暖かくして様子を見ましょう。
・震える、体を丸める
・手足の先が冷たい
・水を飲む量が減る
・舌が白っぽくなる
・朝の食欲が低下する
・おしっこが薄く、無臭
・便が緩く、黄色っぽくなる
・お腹がゴロゴロ、キュルキュル鳴る
また、夜に手足や耳が痒くなる場合は、冷えが原因の可能性があります。ただし、逆に熱が強い場合も痒みが出るため、ペットの様子を見ながら温度調整をしてあげましょう。
体が冷えると起こる不調や病気
寒くなる秋や冬、夏場の冷房などによって、ペットの体が冷えて不調や病気を引き起こす可能性があります。例えば、冷えによる胃腸症状や皮膚の乾燥、炎症などの症状が悪化するなどです。
また、東洋医学的には加齢の症状である腎虚ですが、冷えの症状でもあるとされています。そのため、寒さが腎臓の不調や腎不全を悪化させることも珍しくありません。
冷えによる臓器への血流悪化によって肝機能が弱り、肝臓の数値が上昇する子もいます。咳や肺水腫、ふらつきなどの心不全症状の悪化も多いです。寒さによって血圧があがり、循環が悪くなり、心臓に負担がかかるからです。
一方、脳への血流が制限されると、てんかん発作や脳炎の症状も現れやすくなります。手足や関節への血流が悪化すると、関節に負担がかかり、動き始めに関節に痛みや違和感を感じることもあり、そのまま放っておくと、ヘルニアや関節炎など整形疾患の原因になります。
気になる症状がある場合は、早めにかかりつけの動物病院に相談することが大切です。
冷えに注意すべきペット
冷えに注意すべきペットとして、以下のような特徴が挙げられます。
・シニア
・子犬や子猫
・南国の犬種
・日本犬
・ブルドック
ただし、冷えやすいかどうかはその子によって異なります。日頃暑がりか寒がりか、水をよく飲むのかそうではないかなど、普段の様子をしっかりと観察しておくとわかりやすいです。
体が冷えやすい子には、「暑さに強い」「普段からあまり水を飲まない」などの特徴があります。このような特徴がある場合は、特に注意して観察しておきましょう。
ただし、寒さに強い犬種でも、冷えやすい子はいます。冷えのサインに気づくためには、普段からその子の様子を観察しておくことが大切です。
体を根本から温めよう!ペットの寒さ対策に役立つ東洋医学の基本

東洋医学では、ペットの寒さ対策として「体の根本から温める」ことが重要とされています。冷えが原因で症状が出ているのであれば、症状を抑えるだけではなく、冷えを改善することが大切です。ここでは、ペットの寒さ対策に役立つ「気の巡り」の重要性について解説します。
気の巡りと冷えについて
東洋医学では、「気の巡りが滞る」と冷えが起こると考えられています。これは、もともとの体質、ストレスや運動不足などが原因です。一方で外気や食事、生活習慣などで体が「冷える」と、気の巡りが滞り「気」の動きそのものが鈍くなります。
結果としてますます血流が悪くなり、内臓機能も落ちてさらに冷えが進行する、という悪循環が起こってしまうのです。
体を温め気の巡りを整えるのが重要
東洋医学では、「なぜ体が冷えているのか」「どの部分から冷えがくるのか」を、見極めることができます。そのため、冷えているからただ温めるだけではない対処が可能です。
具体的には、冷え=腎虚(腎の衰え)という状態と考え、漢方薬で腎を助けて冷えの改善を目指すことが多いです。また、胃腸が冷えているなら、胃腸を温めて胃腸機能を改善するのに特化した漢方薬を使用することも可能です。
どの部分がなぜ冷えているのかを見極めてその子に合った方法で体を温め、気の巡りを整えることが重要です。
症状を抑えるだけの治療には注意
冷えが原因で胃腸に不調が起こり、吐いたり下痢をしたりする子が動物病院に行くと、胃腸炎と診断されて嘔吐止めを処方されることが多いです。しかし、本当は冷えが原因なのに症状だけを抑える(制吐剤など)治療を行っても、根本的な解決にはなりません。
その他にも、冷えが原因の皮膚炎でステロイドが処方されることもありますが、これも根本的な治療にはならないのです。
冷えが原因で起こっている場合は、症状を抑えるだけの治療ではなく、冷えを改善するための治療が必要になります。
体の内側・外側からアプローチ!取り入れたいペットの寒さ対策

ペットの冷えは、寒暖差が影響していることが多いです。特に、気温が低下して体も冷えやすくなる夜は注意が必要です。すぐに取り入れられる、ペットの寒さ対策を紹介します。
室内環境の工夫
「ペットは室内にいるから大丈夫」ということはありません。室内でも体は冷えていくため、ペットに合わせた寒さ対策が必要です。
・エアコンは20〜23℃を目安にその子その子の様子に合わせて保温
・床からの冷え対策にマットやベッドを活用
・夜だけ腹巻をする
・直接暖房に当たらないようにする
・室内の温度差が大きくならないようにする
特に秋から冬にかけての季節の変わり目は、早朝・夜とお昼の温度差で体調を崩す子が多いです。室内で過ごしている場合でも、その子の様子を見ながら温度調整をしてあげましょう。
参考:公益社団法人大阪府獣医師会「動物豆知識 防寒対策・熱対策(熱中症)」
散歩や外出時のポイント
散歩や外出時は、できるだけ暖かい時間帯を選び、服や靴下で冷えやすい部位をガードしてあげると寒さ対策になります。気温の低い早朝や夜間は避けるようにしましょう。
また、散歩や外出前にはできるだけ気温差をなくすために、室内で軽く体を動かしておくのがおすすめです。帰宅後は冷えた体や肉球を拭いて、温めるケアをしてあげましょう。
漢方薬で内側から整える
冷えている子には基本、温める漢方薬が必要になることが多いです。しかし、炎症がある場合は、温めすぎたりすると炎症を悪化させてしまうことがあります。
そのため、その子の体質を見極め、温めすぎない量や炎症に対応しながら温めるなどの対応が必要です。治療のバランスや量に気をつけて、今の状態に合わせた漢方薬治療を行うことで、根本的な改善につながります。
ペットの寒さ対策についてよくある質問
Q. 漢方薬を飲み始めると、どれくらいで冷えの改善を実感できますか?
その子の体質や冷えの強さによって異なりますが、早い子だと1〜2週間ほどで「朝の食欲が戻った」「元気になった」などの変化が見られることがあります。腎虚や胃腸の冷えが深いタイプの子は、体質が整うまでに時間がかかることもありますので、獣医師と相談しながら経過を見るのがおすすめです。Q. 漢方薬は冬の間だけ飲めばいいのですか?それとも継続が必要ですか?
季節の冷えが原因の場合は冬だけの服用で改善することがありますが、もともと冷えやすい体質の子は、少し長めに続けることで体の巡りが整い、より安定しやすくなります。どちらが合っているかは、その子の状態を診たうえで判断するのが安心です。Q. 服やマット、暖房などの寒さ対策だけでは不十分ですか?漢方を併用するメリットはありますか?
外側からの保温対策はとても大切ですが、冷えやすい子は内側の巡りが低下していることが多いため、外側の対策だけでは根本的な改善にならない場合があります。漢方薬は冷えの原因に合わせて調整できるため、寒さによる不調の予防や体質改善につながるメリットがあります。
まとめ|ペットの寒さには根本から対策するのが重要!
ペットの冷えのサインを見逃すと、腎不全や胃腸症状、皮膚の乾燥、その他の症状が悪化するなどの不調や病気を引き起こす可能性があります。日頃の様子を観察したうえで、「水を飲む量が減っている」「手足の先が冷たい」などの症状がある場合は体を温めるケアをしてあげましょう。
冷えによる不調がある場合は、その症状を抑えるだけでなく、どの部分がなぜ冷えているのかを見極めて根本から改善を目指すことが大切です。
ペットは寒暖差が冷えにつながりやすいため、気温が下がる早朝や夜の散歩・外出は避け、腹巻やマットなどを活用して寒さ対策をしてあげましょう。ペットの寒さ対策では、日頃からしっかりと観察をして、その子に合った方法で対策することが何よりも大切です。

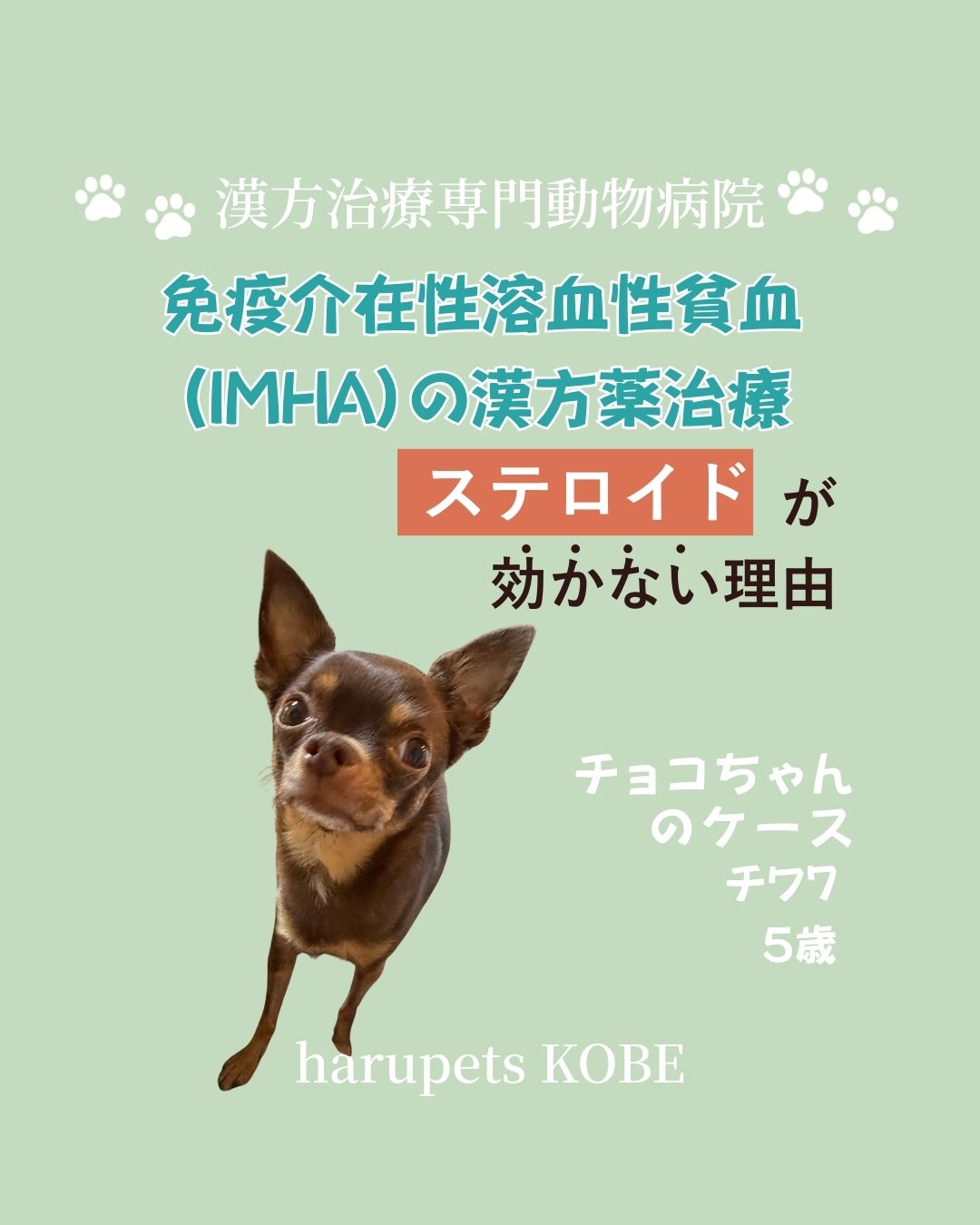

で漢方薬治療しているプラムちゃん.jpg)